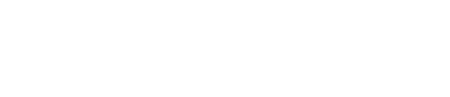ご先祖様への手紙です。供養、追善のために墓地に立てる細長い木の板です。
卒塔婆の歴史

卒塔婆(そとうば)は、古代インド語「ストゥーパ(Stūpa)」に由来する仏教用語で、釈尊の遺骨を納めた仏塔や供養のための塔を意味します。仏教が中国から日本へ伝わる中で、この言葉が「卒塔婆」と音写され、のちに「塔婆」「塔」と略されながら、人々の祈りの文化に根づきました。現在の木製の卒塔婆は、この仏塔の思想を簡略化したもので、戒名や梵字を書き供養のために墓前に立てる習慣は、仏教の「追善供養」の考えに基づいています。追善供養とは、生きている者が善行を積むことで故人の功徳にもなるという教えで、卒塔婆を立てる行為自体が善行とされ、故人への祈りを形として表す大切な行いとされています。
日の出町の卒塔婆製造の歴史
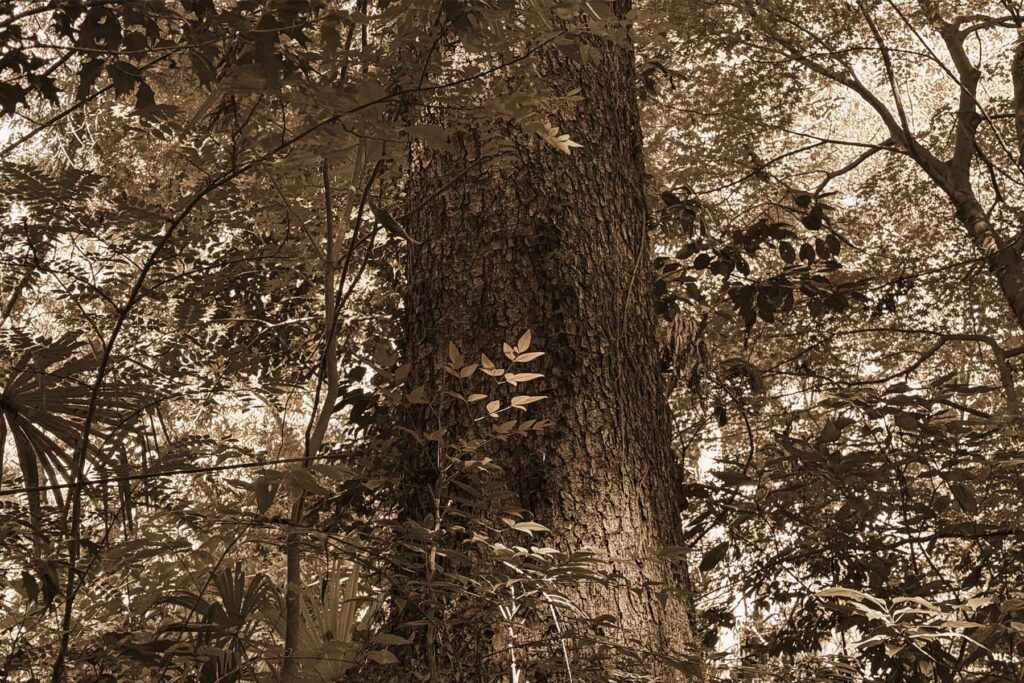
日の出町文化財保護委員会編『日の出町の昔ばなし』によれば、弊社の所在する日の出町大久野地区では、元禄時代(1688〜1704年)にはすでに卒塔婆づくりが始まっていたと伝えられ、その歴史は三百年以上に及びます。多摩地域は江戸のお寺から距離が近く、良質な材木が手に入ったことから、卒塔婆や護摩札の製造が盛んになった地域でもあり、大久野もその代表的な産地として発展してきました。弊社は、この歴史と文化を背景に代々技を受け継ぎ、地域に根づく卒塔婆づくりを大切にしてきた材木店です。伝統を尊重しつつ、一つひとつを真心込めて丁寧に仕上げる姿勢を守り続けています。